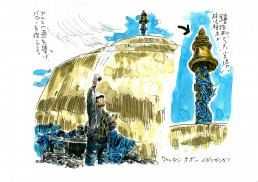モンゴル紀行 〜 オレはテムジン!
雪国新潟の小さな町で生まれ育った子どもの頃、蒙古(内モンゴル)に渡って馬賊になりたいと真剣に思った。
だが、十二、三歳のガキに、当時の日本軍が中国本土で、欧米列強を巻き込んで暗躍した世界情勢や、馬賊というものの実態を理解できるはずもない。
ウブな少年の心を掻きむしったのは、一冊の本だった。檀一雄の『夕陽と拳銃』という本だ。実在の人物で、伊達家の子孫、伊達順之助をモデルにした小説で、主人公の伊達麟之助が満州に渡り、馬賊の首領になって満蒙独立運動に活躍する。
満蒙独立というのは、中国に日本傀儡の満州国」を打ち立てようとする侵略政策だった。その混乱の中で、大小無数の馬賊集団が暗躍した。軍部の実働部隊としての馬賊、それに抵抗するレジスタンスと馬賊、あるいはそうした混乱に乗じて略奪に走る馬賊などが入り乱れていた。
だが、当時の私には、何が正義で、何が悪なのかはどうでもよかった。既存の価値観をぶち壊して、自由と本能を謳歌する男たちの生き様が眩しかった。ただ、大草原を馬で疾走し、モーゼル拳銃を片手に暴れ回り、草原の彼方に沈む、ばかでかい夕陽を見て男泣きに泣きたかっただけだ。
因みに、伊達燐之助(順之助)は、抗日の中国軍に捕らえられ、戦犯として1948年に銃殺刑に処せられる。一切の抗弁も、助命も拒否して死に臨んだその最期もまた、男として華々しく潔く、胸に染みた。伊達燐之助は、少年のヒーローだった。彼が生きた蒙古(モンゴル)に行きたい、と強く思った。
もしかしたら、それは自由を押さえ込まれて、日々を悶々として暮らす雪国の生活に対する反動だったかもしれない。実際、昭和三十年代は、戦後の高度成長期を迎えていたとはいえ、新潟の小都市では実感が乏しく、一年の半年近くは豪雪に埋まる暮らしを、大人たちは諦めたように従順で覇気がなく、少年らしい将来の夢や希望を持ちようもなかった。少なくとも子どもの目にはそう映った。鬱積した心で、故郷も家族も嫌悪した。
もう一つ、檀一雄の『夕日と拳銃』という小説に、生きた血を注入してくれた男が身近かにいた。当時、我が家の近くに決まった日に市が立ったが、その中に生花の露店を出す隻腕の香具師が、満州の馬賊上がりの男だった。
争いで片腕を失ったという男は、いかにも大陸帰りらしい気骨と憂いを隠して、人当たりがやさしかった。私はすっかり彼になつき、市日を楽しみに待った。学校がはねると急いで家に帰り、彼の露店に入り浸った。蒙古の果てしなく広い草原や砂漠、移動しながらゲルと呼ばれるテントで暮らす遊牧民たち。落ちてくるような大きくて真っ赤な夕日と、大地から根を生やしたような巨大な虹。英雄、チンギス・ハーンの話等々、話に胸躍らせた。
チンギスハーンは、モンゴル帝国の初代の皇帝で、モンゴル各地に分かれて抗争を繰り返していた遊牧民諸部族を一代で統一し、中国、中央アジア、イラン、東ヨーロッパなどを征服、人類史上最大規模の世界帝国を築き上げた、モンゴルの英雄。日本でも成吉思汗として知られ、子どもの頃に井上靖の『蒼き狼』を読んで、胸を躍らせた。また後年、「成吉思汗は源義経だ」という奇想天外な説が流布して世間を騒がせた。
日本人も同じモンゴロイド。チンギスハーンと同じ血が流れていると思うと、体が熱くなった。ひそかに自分の尻を鏡に映して、蒙古斑と呼ばれる青い痣の痕を確認して、一層親近感を強くした。
その一方で、チンギスハーンが、右肩甲骨に一つ余分の肩峰突起(けんぽうとっき)があり、それが彼の血筋の特種な遺伝だと知って、自分の肩を真剣に探って見つからず、がっかりした。
(しかし、私はのちに、憧れのモンゴルを訪れたときに、遊牧民の人々から親しみを込めて「テムジン」という蒙古名(モンゴルネーム)で呼ばれた。テムジンは、かのチンギスハーンの幼名で、私の容貌がチンギスハーンにそっくりだというのだ。私の昂揚は頂点に達した。)
「いざ、モンゴルへ」
憧れの地、モンゴルの大草原が目の前にある。見渡す限り、緩やかな起伏を描いて緑の草原が続く。柔らかいフェルトのような大地だ。その乾燥した地表に、水の幻想を抱かせながら陽炎がユラユラと踊っている。そして、空の雲の厚さ薄さを透かした陽が、まだ生え揃っていない夏草の濃い緑や萌黄色、枯れた黄褐色といった色の変化を、縞模様に描き出している。
モンゴルの大草原の偉大さは、地上の一点から眺めているだけでは分からない。もし天空から俯瞰して、草原の中に人間の痕跡を探そうとするなら、小さな吹き出物の丸い絆創膏のような遊牧民のゲルと、蟻がのたくったような轍の痕跡だけだ。しかしまた、モンゴルの大地はあまりに広大で不毛なるがゆえに、遊牧民は水や青い草を求めて移動しなければならず、ゲルやラクダに引かせた荷車の轍の跡は、わずかの間に土埃に消されてしまう。
なんという仮借のない土地だろうか。だが、その過酷な自然は、人々に絶望や諦めを喚起しない。それどころか、人々は境遇を恨まず、他者に依存しない不屈の強靭さを身につけていく。果てしない地平線の先に、壮大なロマンを駆り立てることができる。それこそが、チンギスハーン以来、培われてきたモンゴル遊牧民の血だ。
大地が放射するエネルギー、自然の精霊の力のようなものを感じる。
少年時代に夢想した心の原風景が、少しの違和感もなく体を包み込んでいる。心象の故郷を探し当てたような、懐かしさと安らぎに満たされている。これからの旅で起こるすべてを、素直に受け入れることができるという確信のようなものが湧き上がっていた。
本格的な旅をスタートさせた初日、ヘンテイ山地の東の草原で早くも道に迷った。ウランバートルから600キロ離れた東北部の、ロシア国境に近いダダルに向かう途中だった。ダダルは、世界を支配下においた大モンゴル帝国の始祖、チンギス・ハーンの生誕地で、死後の埋葬地だといわれている。モンゴルの長旅の真っ先に訪ねておきたかった。ダダルは、首都のウランバートルから北に位置して、地図で見る限り距離はそう遠くはないが、出鼻から方向を見失って、草原の真っ只中に取り残されてしまった。
モンゴルでは、首都のウランバートルの市街地を出ると、道らしい道はなくなってしまう。地図も満足なものがない。あっても、日本の4倍もの国土のほとんどは手つかずの草原や砂漠地帯で、あまり役に立たない。目印になるものもほとんどない。目標になるかと思われる遊牧民のゲルも、いつ移動するか分からない。
どこまでも見通せる大地に刻まれた轍の跡は、強風が吹くと砂煙で消されてしまう。そのため、轍の跡は途中で消えたかと思うと、離れた場所に突然新しい轍が出現する。轍の跡を追いすぎると方向感覚が狂って、いつの間にか逆方向に走っていたりする。
そのためモンゴルの旅では、ウランバートルで信頼できるガイドや運転手を雇うしかない
初めての旅で雇った運転手は、物静かで誠実そうな男だった。車は彼の持ち物で、旧式のロシア製の箱型ジープだった。車はだいぶ傷んでいて不安があるが、どうやら選択権はなさそうだ。腹をくくって身を委ねるしかなさそうだ。成るように成るさと、荷物を放り込んで、出発する。
車は、ウランバートルを出ると、草原を濛々たる土埃をまき上げて疾走した。道路がないから、どこを走ってもいい。平地を選んで走ってもいいし、波打つような丘を一気に突っ切ってもいい。転倒しそうな急斜面を乗り越え、湿地や川を水飛沫を上げて渉る。車は、内臓がこんがらがりそうに激しく揺れ、外よりひどい土埃が舞い込んでくる。
向かい風でラジェーターが干上がって、度々エンジンが止まる。運転手が慣れた様子でラジエーターに水を補給する。再びエンジンがバリバリと動き出す。錆で穴が空いたボンネットがブルブル震える。
「大丈夫?」
「ダイジョウグイ(大丈夫)!」
日本語とモンゴル語で会話が成立する。前途多難な旅を予感させるが、誰も悲観にくれることがない。モンゴル高原の乾いた空気が、暗さを吹き飛ばしてくれる。自然界の悠久の営みの前では、人間の日常の出来事などは、大地の小さな砂粒ほどの重みしかない。何事も笑って受け入れるしかない。
旅の初日は、道に迷ったまま日が暮れてしまい、草原に野営することになった。アセチレンランプの灯で飯を食い、酒を飲んだ。運転手は、何事もなかったように鼻歌を歌いながら、ウランバートルの市場で買い込んできた羊肉を料理した。
平べったい大地を押しつぶすように夜空の闇が濃くなってくると、おびただしい数の星が光を強めてくる。運転手が一番光り輝く星を指差して笑った。
「あれが、黄金の矢を射る星(北極星)だ。モンゴルの遊牧民は、星を見ていればどこへでも行ける」
その夜半に激しい雨が降って、あわてて車に逃げ込んだが、翌日は朝から晴れて、もう道に迷うことはなかった。昼は、太陽が分刻みに時を教えている。運転手は自信に満ちた顔をしていた。
雨の上がった草原をひた走り、オノン川を北に遡り、ダダルに向かう。
途中、遊牧民のゲルに立ち寄った。草原にポツンと立つ一本松が目印で“ウルゲンナルス(広い松)の遊牧民と呼ばれているという。ストーブ兼用のカマドの火と、暖かいお茶で歓待してくれた。
モンゴルの遊牧民は、見知らぬ旅人を誰でも無償で迎え入れてくれる。望めば食事も用意してくれるし、泊めてもくれる。この広大な草原や砂漠を移動して生きる宿命を負う遊牧民にとって、助ける者と助けられる者の立場が当たり前のように入れ替わる。自然環境が過酷であればあるほど、人との繋がりが命の支えになる。偉大なモンゴル民族の強い団結力の源でもある。
人と人との繋がりは、物理的な距離が遠いほど精神的な距離が近くなり、物理的な距離が近いほど精神的な距離が遠くなる。それは、人口が少ない田舎人の人情の濃さや、人口が密集した都市生活者の、精神的な病理にも当てはまる。
ダダルは、ロシア国境の森に囲まれた小さな村だった。北方に位置する村は、雨が多く冬は厳冬になるため、ゲルは少なく、丸太小屋が点在している。
美しい湖の畔に、コンクリート造りの生誕記念碑があった。巨大なチンギス・ハーンの像が見下ろしている。見ていると、他人のような気がしない。我ながら風貌が似ている。同行している運転手や、周りを取り囲んだ村人が、顔を覗き込むようにして笑った。
憧れのチンギス・ハーンに似ているといわれることが素朴にうれしく、誇らしい気持ちになった。
その後、長く滞在することになったセルゲレン草原の遊牧民ドンドフさんに、
「あなたは同じモンゴル人の血が流れている。ハーンによく似ている」
と真顔で言われ、「テムジン」という蒙古名(モンゴルネーム)を貰い、乳酒で祝杯をあげた。それが、遠方からの客をもてなす方便だとしても、遠い祖先との距離が近くなったようでうれしかった。その後の長い旅の途中でも、私は「テムジンさん」と親しみを込めて呼ばれた。
「オレはテムジン!モンゴルの英雄、チンギス・ハーンの末裔なのだ!」
と、いうことにしておきたい。